ホスファチジルセリンは体内で生成出来、一部は体内生成が出来ない物質であり、細胞膜を構成しているリン脂質の一つです。
ホスファチジルセリンは特に脳に多く存在していることから、脳機能維持に極めて重要であるとされています。
認知症予防で注目されている成分ですが、集中力、記憶力、判断力等の向上に有効的と言われ、ストレス社会を生き抜く上で重要な成分として注目されています。
Table of Contents
体内生成
ホスファチジルセリンはアミノ酸の一つであるセリンと、ホスファチジン酸が縮合することによって生成されたリン脂質の成分です。
脳に多く分布されており、体内に存在するリン脂質の1割が脳に存在すると言われます。
脳に存在するホスファチジルセリンは、体内で生成することが出来ないため、食品から摂り入れる必要があります。
食品から摂り入れたホスファチジルセリンは、そのままの形態では血液脳関門を通過できませんが、体内吸収後、一旦分解されてから、セリン、ホスファチジン酸が各々血液法喚問を通過し、脳内でホスファチジルセリンに再合成されます。
膜として輸送を正常に行う
ホスファチジルセリンは細胞膜の内葉、つまり細胞質側に存在し、膜としての役割を担います。
蛋白質の働きの一つに、物質を細胞内外に輸送するというものがあります。
細胞内に必要な物質を自ら送り、細胞内の余分な電解質を細胞外に排出するというポンプ作用としての働きを持つとともに、チャネルというこれらの通り道を作る役割を担っているのです。
また、全ての物質を輸送するのではなく、必要な物質のみ細胞内外に輸送するように調節します。
ホスファチジルセリンは、膜蛋白質を細胞質の中に留めることで、輸送として柔軟性のある働きを支えることで、この働きを正常に行えるように支えています。
神経細胞を正常に働かせる
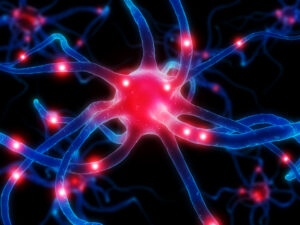
ホスファチジルセリンは、神経細胞のダメージから守ることにより、学習力や記憶力を高め、加齢やストレスによる脳機能低下の予防に期待があります。
認知症予防
ホスファチジルセリンは脳細胞の構成物質です。
脳内でホスファチジルセリンは、神経伝達物質に関わるホルモンの分泌を促します。
ホスファチジルセリンは、脳細胞内の物質の酸化を防いだり、脳細胞の膜を軟らかくすることによって、神経の伝達が円滑に行えるようにサポートします。
脳細胞の膜が軟らかく成れることで、神経細胞の新陳代謝が活発になり、細胞内部の老廃物の排出と新しい栄養の供給が繰り返されることになります。
神経細胞の働きが活発になると神経間の情報を伝達しやすくなり、更にホルモン分泌が促進されることから、脳機能向上に期待があります。
また、脳の酸化を防ぐことは、脳の細胞の損傷を防ぐことになるため、認知症のリスクを低減させると言えます。
神経細胞は、神経成長因子(NGF)を生成し、これを利用することで認知機能を維持しています。
ホスファチジルセリンは、NGFの産生を高める、NGFの受容体の機能維持としての働きに期待があります。
このようなことから、アルツハイマー型認知症の予防に期待があるのです。
ストレス対策
ホスファチジルセリンは、脳の新陳代謝を促進させることから、認知機能低下や学習能力向上の他に、集中力や意欲の向上、怒りの感情の緩和といった役割もあり、ストレスによる脳のダメージの軽減を図ることに期待があります。
ホスファチジルセリンを含む食品
ホスファチジルセリンは、大豆をはじめ、青魚、カツオ、レバー、白いんげん豆等に含まれます。
また、EPAやDHAと一緒に摂ると、相乗効果によって脳の血流を促し、脳機能を向上させます。
そして、抗酸化作用のあるビタミンA、C、E、ファイトケミカル、ポリフェノール、フラボノイドと摂ると、活性酸素による脳のダメージを軽減する作用が相乗されます。
まとめ
ホスファチジルセリンは、体内成績出来ない上に、加齢やストレスにより減少を加速させてしまいます。
その為、ホスファチジルセリンを日常的に食品から摂り入れる必要があります。
サプリメントから摂取する場合は、1日当たりの使用量を守りましょう。
1日あたりの摂取量の目安は200~300mgを継続すると良いとされています。
ホスファチジルセリンを摂取することも大事ですが、特定の食品や栄養素に拘ることより、身体に良い食材をバランス良く、出来るだけ多くの品目を摂り入れましょう。
認知症予防の食事については、mind食も参考にしてみて下さい。
ジャンクフードの日常的な摂取は、体内にヒドロキシノネナールやAGEsを増やす原因になり、認知機能の低下を招きやすくなります。
腸内環境の悪化、リーキーガットによるタイトジャンクションの異常による栄養吸収不良を招かないためにも、腸内環境を整えることも大事です。
過度な飲酒、運動不足、睡眠不足も認知機能に支障をきたすため、嗜好品は過度にならない程度に留め、息がはずむ程度の運動、適度な睡眠、日光浴等も取り入れていきましょう。


